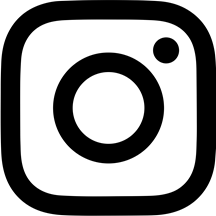延長戦かゲームチェンジか? 経済学者と語る、資本主義社会の未来予想図(前編)
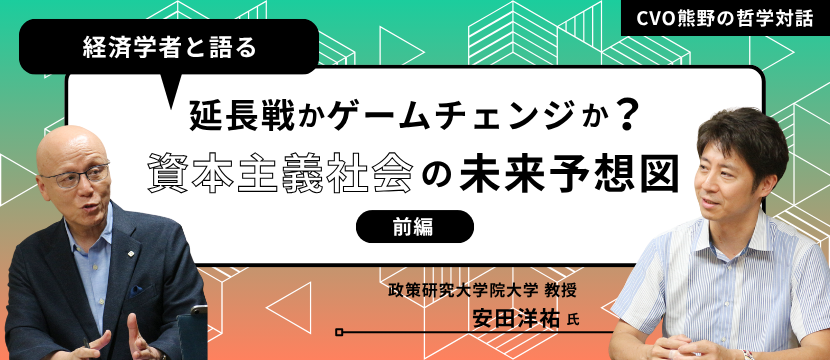
今回、当社代表取締役会長の熊野英介が対談したのは「ゲーム理論」や「マーケットデザイン」を専門とする、経済学者の安田洋祐氏。
資本主義や民主主義など、戦後日本を支えてきた社会システムのほころびが露わになる昨今。前代未聞のAI革命が起きるなか、日本はどう対応すべきなのか――?安田氏の経済学的知見と鋭い市場洞察に、熊野が持つ哲学的かつ事業家としての視点がクロスすることで、大局から時代の潮目を読む貴重な対談となりました。
(対談日:2025年7月7日)
目次
- 私たちは数字の概念を見つけて、世界を広げている
- 市場を動かすのは虚か実か?時代が生んだ資本主義の加熱
- プロテスタンティズムと資本主義拡大の意外な関係性
- 企業の責任を追うのは個人?機関?民主主義に通じる責任の拡散
- 既存の社会システムを変える、マーケットデザイン的方法論
私たちは数字の概念を見つけて、世界を広げている
熊野:環境問題の深刻化、国際秩序の動揺、そしてAIなどによる技術の激変。これらが重なり合う今は、まさに"歴史の転換点"だと感じています。この流れの中で、大きなゲームチェンジが起きるのか、それともこれまでの延長戦が続くのか。安田先生のご著書『日本の未来、本当に大丈夫なんですか会議』のタイトル通り、経済学の視点から忌憚ないご意見をいただきたいです。
安田氏:はい、本日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします。
熊野:まずは安田先生の専門分野である「ゲーム理論」について。これはどのような学問ですか?
安田氏:経済学には、ミクロ経済学、マクロ経済学、そして統計的な要素を持つ計量経済学の3本柱があります。ゲーム理論はこの3つの中で言うと、ミクロ経済学で主に使われる数理的なツールにあたります。小難しい解説を加えると、複数の主体をプレイヤーとみなし、互いに与える影響を考慮しながらその意思決定や行動を分析する学問です。
戦略的な駆け引きを扱うゲーム理論の面白さに大学3年生のときにハマってしまって、気がついたら海外留学までして博士号を取り、研究者になっていました。
熊野:経済学は日本では文系科目ですが、ゲーム理論は関係性に依存する不確実な要素に加えて、すごく数学的な側面も持っていますよね。安田先生は昔、数学では代数学と幾何学のどちらがお好きだったんですか。
安田氏:僕は断然、幾何学ですね。図形の問題が大好きでした。
熊野:最初に仮説を立てて論理で詰めていく代数学に対して、幾何学は全体を俯瞰して補助線を引くなど「あ、そういう解き方があったのか!」という発見があるので、ワクワクドキドキしますよね。
安田氏:おっしゃる通りですね。代数の問題は、変数をxに置き換えて数式を立てるなど学校で学ぶ「テクニック」が重視されますが、図形の問題は「ひらめき」が求められます。どちらも大切ですが、個人的には方法論より感性が試される図形の問題が大好きでした。ゲーム理論もパズル的な要素がかなりあって、幾何学の問題と同じく発想力が必要です。
熊野:冒頭から脱線しますが(笑)、図形の話から連想して、1ついいですか。
中世まで、数学や美術における空間理解は、基本的に「平面の上でいかに現実的に見せるか」という姿勢に基づいていて、画家たちは限られた2次元のキャンバスに、あたかも3次元のような奥行きや立体感を演出してきました。その典型例がレオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』です。この絵は、遠近法を用いて空間の奥行きが描かれていますが、実際の配置に置き換えようとすると、登場人物やテーブルのサイズなどにおいて、リアルな写実とは矛盾が生じます。そこには「虚(錯覚)」を「真(現実)」のように見せることで精神的中心としてのキリストを際立たせるという芸術上の工夫が存在したわけです。
 レオナルド・ダ・ヴィンチ 『最後の晩餐』(1495年-1498年)
レオナルド・ダ・ヴィンチ 『最後の晩餐』(1495年-1498年)
熊野:ところが近代に入ると、空間の捉え方そのものが変化していきます。ルネサンス(※1)以来の遠近法は、2次元の平面上に3次元空間を仮想投影する仕組みでしたが、19世紀の非ユークリッド幾何学(※2)の発展によって、空間は必ずしもユークリッド幾何学的ではない、例えば、それまで交わることは決してないとされていた平行線が交わる場合もあると理解されるようになりました。これにより、従来の「仮想的に3次元を描く」という発想から、空間そのものの構造を問い直す方向へとシフトしていったのです。
※1:ルネサンス...14~16世紀、イタリアを中心にヨーロッパで展開された文化、芸術の運動。人間中心主義(ヒューマニズム)を掲げ、中世の神中心の考え方からの脱却を図った。
※2:非ユークリッド幾何学...古代ギリシャのユークリッドが体系化した「ユークリッド幾何学」の常識を覆す学問。その一例である「球面幾何学」の分野では、三角形の内角の和が180度を超え、平行線は存在しない。一方「双曲幾何学」では三角形の内角の和が180度未満となり、平行線が無数に存在する。
僕は、社会や経済の進化も、数学や芸術における次元の拡張のように理解できると考えています。
かつての社会は、共同体内における物々交換の経済が中心でした。僕は、この顔の見える範囲での相対した1対1の経済関係を「1次元社会:点的な交換」と定義しています。これが、貨幣の登場により「貨幣価値」を媒介とする交換へと移行したとき、経済活動の範囲は共同体を越え、関心領域が面的に広がった交換社会が始まります。これを「2次元社会:貨幣による面的拡張」とします。そして世界は産業革命を迎えます。産業革命は、協業と分業によって労働生産性を飛躍的に高め、「労働時間×資本」を基軸に、モノを大量生産・安定供給する複雑な工業社会を確立しました。工業社会における企業の競争力の源泉は、「現場・現物・現実」に裏付けられたリアリズムと唯物論※です。これを「3次元社会:工業化による立体的生産」としましょう。
※唯物論...世界や宇宙の根源を物質に置き、精神や意識は物質から生じる副次的な現象と考える哲学的な立場。
そして今、生成AIの発達等により、社会は「労働時間×資本」ではなく「価値×資本」が基軸となる新しい段階に移行しつつあります。効率以上に、生み出す価値の質が重要になるこの社会には、時間・関係性・体験といった新たな要素が組み込まれ、企業活動は「4次元的」な広がりを持つはずです。私は経営者として、今まさに「4次元社会:価値創造を資本と結び付ける時代」に足を踏み入れていると感じています。
先ほどお話ししたように、僕はこの変化を数学や物理学におけるパラダイム転換と重ねて理解しています。非ユークリッド幾何学は、平行線は交わらないという従来の常識を覆し、枠組みそのものを転換しました。この"常識を超える思考"は、20世紀以降の科学にも通じます。相対性理論は空間と時間を一体の「時空」として再定義し、カオス理論※は不確実で複雑な系(システム)の中に新たな秩序を見いだしました。さらに量子力学は、粒と波、虚数と現実のあいだで「存在のあり方」を問い直しました。これらはいずれも、既存の枠組みでは説明できない現実に直面したときに生まれた思考転換だったのです。
※カオス理論...一見ランダムで予測不可能に見える現象の後ろに、実は決定論的な法則が存在することを示す理論。身近な例として、気象予測、水道の蛇口から落ちる水滴のリズムなどがある。
ビジネスの世界でも「1次元から4次元」への移行は、枠組みそのものを更新することを意味しています。社会と経済は「1次元=物々交換社会」から「2次元=貨幣経済社会」「3次元=工業社会」を経て、今「4次元=価値創造社会」へと進化の歩みを進めているのではないでしょうか。
かなり独自の見立てなので、伝わるか不安ですが、これからはモノや労働の効率ではなく、信頼できる関係性や情報や文化性といった無形性の資本を組み合わせて価値を生み出す「価値競争」の時代になると、僕は考えています。
安田氏:非常に面白い観点ですね。
先ほどのお話にあったように、世界を平面的に見ていると平行線は当然交わらない。でも、立体的な球体を考えると、僕たちは初めて交わる平行線をイメージできるわけです。
同様に、古代の人々は図形や立体からマイナスの数をイメージできませんでした。マイナスの数の発想は、数直線の中央に0を置くことで初めて生まれます。そして、ひとたびその概念を導入すると、例えば「航海で東へ進んだ後、嵐で西へ戻った」といった状況説明に非常に便利だと気づくわけです。現代で例えると、多くの人は「2乗するとマイナスになる虚数」に抵抗感があると思いますが、図形を回転させる状況では、虚数がある方が世界をイメージしやすくなる。つまり僕たちは、新しい数の概念を見つけるたびに、世界を広げているんですよね。
数学の命題や定理によって我々の世界観が変わり、そこから科学や算術、さらには商工業が発展する。これらは全部ひとつながりの事象だと思います。
市場を動かすのは虚か実か?時代が生んだ資本主義の加熱
熊野:先ほど空間の捉え方の視点から社会や経済の立体化のお話をしましたが、今、安田先生から出た虚数のお話、これは時間の捉え方に大きく影響しますよね。虚数は時間軸の観点から4次元空間の表現に大いに役立っていて「空間の3次元(縦・横・高さ)」+「時間の1次元」で構成される4次元空間は世界を正確に理解するために必要不可欠な理論的拡張です。
僕は、虚数が時間を空間に取り込み拡張させたように、これからは共感や美意識といった実体のないものが、社会を拡張する時代になると思います。
すでに我々は30年も前から、ECサイトという仮想空間上の取引が現物の流通を動かす体験をしていますし、GAFAM※の出現や、ビットコインなどの仮想通貨の社会浸透からも「虚」というリアルでない価値が現実社会に組み込まれていることは明白です。
※GAFAM...アメリカの大手IT企業であるGoogle、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoftの5社の頭文字をとった略称。
そう考える前提として、まず、AIがここまで発達した社会では価値を生み出す源泉は「信頼できるデータ×情報を洞察して意味を与えるインテリジェンス」になりますが、ここでデータの信頼性はブロックチェーンが、情報をインテリジェンスに高める役割は生成AIが担えます。
また、これまでの「生産したものを交換する"生産価値交換社会"」から、「価値そのものを生み出し交換する "価値生産交換社会"」に移行すれば、従来の取引コスト(取引における情報収集・交渉・契約・監視・信頼確保等のコスト)が大幅に削減されます。そもそも、自然の生態系には取引コストがありませんよね。例えば植物が光合成して放出した酸素を動物が呼吸に使い、その排泄物を微生物や植物が分解して栄養にして循環させる、この過程には契約や監視は存在しません。我々の社会でも、ブロックチェーンによって信頼の保証が自動化され、生成AIが情報収集を自動化することで、取引コストが大幅に削減されていくことでしょう。
では、このような価値生産交換社会において、我々人間は何を求められるのか?僕はそれが、共感であり、美意識であると考えます。これまでのモノの便利さや合理性よりも「意味」や「共感」に価値を見出す、その美意識こそが競争原理となると思います。この美意識が拡張する社会が、先に述べた「4次元の価値創造社会」であり、その交換領域は、未来の希望や理想の実現という、共感できる美意識の範囲になります。人間の美意識の方向性が未来に向かえば、価値は時空間を超え、まさに4次元的な社会拡張の時代が訪れると考えています。
マーケットデザインを専門とする先生は、どのようにお考えでしょうか?
安田氏:こちらも壮大で面白いテーマですね。
まず、僕は虚実の定義自体が、時代を反映したものだと思っています。昔は「マイナスの数」が虚のような存在だったように、動物にとっては「数」という概念そのものが虚に近いですよね。経済で使うお金も実は同じです。僕たちは千円札や口座残高を「実在するもの」と感じますが、冷静に考えれば、それ自体は食べられるわけでも道具として使えるわけでもなく、他人が交換に応じてくれるから価値を持っているにすぎません。つまり、多くの人が「実」だと思っている千円札も、見方を変えれば「虚」なんです。
そう考えると、今はまだ暗号資産や電子的なトークンについていけない人も多いでしょうが、将来的にはその存在も「実」に近づくのかもしれません。
熊野:おっしゃるとおり、お金そのものは紙や数字ですが、それに価値を与えるのは社会的な合意という「虚」ですね。そういう意味では、法律や契約、国家といった制度も、社会を構成する人々の共同幻想としての「虚」に立脚したものといえます。
安田氏:まさに。ではそのうえで、今の社会の基盤ともいえる「資本主義経済」が生まれ、一定の繁栄を築いたのはなぜか?まずはそこから話を始めましょう。
多くの人は、農業や工業のように、目に見える食料や製品が生まれる活動を「実態のある経済」と考えるし、それに対して金融業は資金の融資や出資といったお金のやりとりが中心で、直接「モノ」が生まれないため、虚業のように見られがちです。ではなぜ、生きるか死ぬかギリギリの生活水準だった人類に、せいぜい200~300年前に劇的な経済成長が起き、それが今日まで続いているのか?この問いに対して、歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏は著書『サピエンス全史』の中で「信用革命」が大きなターニングポイントだったと説いています。
近代以前の封建社会では職業選択の自由はほとんどありませんでした。時間の流れ方も直線ではなく円環的で、毎年同じことを同じ規模感で繰り返しているので、新しいビジネスアイデアはそうそう湧きませんし、そもそも新しいビジネスを始めるには、自分の生活を切り詰めてお金を貯めるしかありません。ところが近代になると、第3者が融資や出資を通じてビジネスを支える「信用革命」が起こり、貯蓄がなくてもビジネスに挑戦できる仕組みが生まれました。誰にでも起業の可能性が開かれ、資本主義が発展する大きな転機となったのです。
僕はハラリ氏のロジックに賛成ですが、個人的には信用革命の他にも2つ、資本主義の発展にとって重要な転換点があったと思っています。1つは、有限責任制を導入した、東インド会社※の登場です。起業家も出資側も、ある程度リスクが限定されていないと、怖くて簡単にはビジネスを始められません。どれだけ失敗しても出資分以上の損害は出ない、つまり命までは取られない、という有限責任の仕組みができたのは大きいと思います。
※東インド会社...政府から特別な認可を得て、アジア貿易の独占権を与えられた会社。17世紀初頭にイギリス、オランダで相次いで設立され、遅れてフランスなどでも設立された。出資者から多額の資金を集め、株式会社の原型となった。
安田氏:そしてもう1つの転換点は、手段と目的の逆転です。お金とは本来、生活を豊かにするための手段です。一定以上の資産を得てしまえば、それ以降暮らしぶりはほとんど変わらず、普通なら欲望も飽和します。ところが、お金は「可能性」、あるいは「権力」の象徴になり得るんですよね。行使するかどうかは別にして、人間の可能性や権力には上限がないので、欲望が飽和しないんです。その結果、富豪たちは消費のためではなく、資産そのものを増やすことを目的化し、際限なく稼ぎ続けます。
資本主義はよく利益が自己増殖する仕組みだと表現されますが、この運動法則がぐるぐる回り続けるためには、信用革命、有限責任、そして手段と目的の逆転という、3つの要素が欠かせなかったのではないかと考えています。今はこの3要素がある程度揃っているので、見方によっては資本主義が暴走しているのかもしれませんね。
プロテスタンティズムと資本主義拡大の意外な関係性
熊野:ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーが1904~1905年に発表した論文『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』では、プロテスタンティズムが資本主義の発展に寄与した可能性が論じられていました。東インド会社を主導したイギリスもオランダも、プロテスタントを主要な宗教とする国ですよね。
マックス・ヴェーバーは、一定のプロテスタント宗派では欲望や贅沢が否定され、生活を労働に捧げる勤勉さが是とされるため、人々は仕事に励み、資本は貯蓄されることなく資本として再投資される。こうした行動が人類の莫大な生産力を引き出し、資本主義の発展をもたらしたと説いています。
さらに僕は、神の道に近づくために前人未到の可能性に挑戦するのが、プロテスタントの特徴ではないかと考えています。つまり、上限なく利潤を追い求める姿勢は、宗教的な思想から生まれたのではないかと。いかがでしょうか。
安田氏:非常に面白い着眼点ですね。先日、東洋哲学・中国哲学の専門家である、中島隆博教授と資本主義についてお話する機会がありましたが、可能性の上限を外す行為について、中島先生もプロテスタンティズムとの関係に言及されていました。
一神教にとって神は、無限の存在です。その神の存在に対峙して、近づいていくために上限を外す行為は、プロテスタント的な世界観だと割と自然なことである一方、日本人を含めた東洋的な世界観からは少し遠いんじゃないか。そう、中島先生がいみじくも指摘されていました。まさに、熊野さんと同じ発想ですよね。
神が超人的な存在であるのに対して、我々一人ひとりは寿命も有限で、できることにも限りがある。人類一人ひとりが神とある程度対峙していくために、神であれば無限のリスクを負うところを我々人間の責任は有限にする有限責任制や、可能性としては無限に存続し得る法人を生み出していく......。これは、筋が通ったアプローチのような気もします。
企業の責任を追うのは個人?機関?民主主義に通じる責任の拡散
熊野:少し話が戻りますが、株式会社が登場した当時、特に銀行のような金融業は会社の借金はすべて出資者が背負う「無限責任」のルールで運営されていましたよね?
アメリカのニュージャージー州は1875年の州憲法改正で、有限責任原則を明確に打ち出して会社設立に関する自由度を高めたことで知られていますが、このとき反対の声が大きかったのは銀行業界だったと思います。「銀行は信用で成り立っている。やるなら無限責任でないと駄目だ」と考えたのでしょう。その後、金融業界に有限責任が広がった後も、世界的に有名な保険市場「ロイズ・オブ・ロンドン」だけは1994年まで無限責任制を維持していましたよね。
安田氏:おっしゃるように、あえて有限責任にしないことで、自分たちのビジネスの正当性を示すという側面もあるでしょう。今でも、例えば法律事務所はパートナーシップ(合名会社)なので無限責任ですよね。弁護士業務は固定費用があまりかからないので、失敗してもリスクが少ないビジネスとはいえ、なかなか難しいことです。
あと、最近僕が面白いと思ったのは、外資系の金融企業「ゴールドマン・サックス」も、元々はパートナーシップだったそうです。それが1998年に有限責任の株式会社になったとき、社内の雰囲気がガラリと変わったそうですよ。パートナーシップのときはある程度の節度があったのに対して、いったん有限責任になってしまうと、どんどんリスクを取って稼げるだけ稼ぐ流れができたと聞きました。
熊野:ロイズ・オブ・ロンドンとゴールドマン・サックスの有限責任化。これらが起きた1990年代は、市場の1つの変わり目だったのかもしれないですね。
株式会社の登場は「企業は誰のものなのか?」という問いも生みましたよね。1919年、アメリカのミシガン州で行われたフォード・モーター社とダッジ兄弟の裁判(ダッジ対フォード事件判決)では、フォードは「会社は経営者の考えで運営するものだ」と主張し、ダッジ兄弟は「会社は株主の利益のために経営すべきだ」と反論しました。判決ではダッジ兄弟の「株主が大事」という主張が認められましたが、ここで注目したいのは、企業の責任は誰が負うのか?という視点です。
個人投資家が多い時代、企業の運営には市民の倫理観や常識がとても重要視されていました。でもバブルが崩壊した1990年代以降、機関投資家が市場で存在感を増しはじめると、企業の運営から「個人」は消えていきます。これは、市民が直接参加して決めていたものが、政治家(代理人)が議会で決めるように変わっていった民主主義の流れにも重なりませんか?
機関投資家が資本主義を動かすようになり、市民革命から続く「自分のために国を作る」近代化の本質が、どんどん変化している気がするんですよね。
安田氏:これは市民の役割は何か、そもそも市民とは何か、という問いでもありますね。
既存の社会システムを変える、マーケットデザイン的方法論
熊野:資本主義と民主主義のメカニズムは、本当にこのままでいいのか?今、その点が究極に問われる時代が来ていると思うんです。そこで安田先生に、社会を変えるにはどのような仕組みが必要なのか、マーケットデザインの視点からお話しいただきたいです。
安田氏:資本主義と民主主義の改革に関しては、2通りのアプローチがあると思います。
1つは、経済も政治も、仕組みからラディカルにアップデートする方法です。例えば貨幣ですね。お金って実は原始的で、制約も大きい仕組みなんですよ。現状では人の経済的な可能性は、お金をいくら持っているかだけで単純に決められてしまいます。例えば、100万円を稼いだ人は100万分しか購買活動ができませんし、最終的にはどれくらいお金を蓄財したかによって、その人の老後の暮らしぶりも決まります。でも、例えば過去の行動履歴をビッグデータ化すれば、個人がどれくらい社会に貢献したかに応じて年金の額を変えるなど、経済の仕組みを根本的に変えることだってできるかもしれないですよね。
これは政治システムでも同じことです。今は定期的に開催される選挙で、1人1票を紙に書いて投票するという古い形式を続けていますが、デジタル技術を使えば、もっと複雑で現実に即した意思決定の仕組みを作れる可能性もある。
経済も政治も、我々の不満を解消してくれるシステムがあるかもしれないのに、この古い制度をいつまで使い続けるのか。もっとアップデートできるんじゃないか?と思いますよね。
もう1つ、現状の仕組みを維持しながら、問題点をある程度克服する代替的な方法として、人々のインセンティブを引き出すマーケティング手法が使えるかもしれません。アプローチの例として、僕が5年前に立ち上げた「エコノミクスデザイン」という会社で展開しているサービスを紹介しますね。
企業が新商品やサービスを出すとき、過去の類似商品の販売データがあれば、需要はある程度予測できますが、全く新しい商品の需要予測を正確に立てることはなかなか難しい。既存の調査手法としては、顧客に「いくら払いたいか」を直接聞く自由回答法とか「AとBどちらの商品が欲しいか」という質問を繰り返していくコンジョイント分析とか、いくつか方法はありますが、消費者が商品に対する支払い意欲を本音で答えているとは限らない。そこで僕たちは、ノーベル経済学賞を受賞した「セカンドプライスオークション」(第2価格オークション)の論理を応用した、新しいマーケティング手法を提案しています。
セカンドプライスオークションはちょっと変わったルールの入札方法で、勝者は1番高い金額を書いた人ですが、支払う金額は本人が書いた金額よりも1つ安い、全体で2番目に高い金額なんです。このルールの下では、各入札者はアイテムに対する価値を割り引いたり盛ったりして入札するインセンティブがありません。たとえば、あるアイテムの価値が1,000円だと思っているときに、そのまま正直に1,000円を入札するのが最善の戦略になる。売り手、つまり主催者からすると、参加者がアイテムに対してどういう価値基準を持っているのかが一発でわかるわけです。この行動原理を利用したのが僕たちのマーケティング手法です。
まず、企業は事前に商品やサービスの価格をあらかじめ決めておき、その価格を伏せたうえで消費者や取引先に商品の価値を申告してもらう。申告額が企業の用意した価格以上なら契約が成立し、企業側が決めた価格を支払う。一方で、申告額が価格を下回れば契約は不成立になる。この条件下では、消費者は商品に対する本音の価値を申告するのが最善となるため、消費者や取引先から正確な評価を得られるのです。
熊野:ビジネスにおいて、買い手と売り手が駆け引きする労力の無駄がないんですね。「正直に振る舞うことが全体の利益につながる」といった、社会契約的な理論とも共鳴しているんでしょうか。
安田氏:たしかに、そういった側面もありますね。おっしゃるように、戦略的にあれこれ考えずに正直に振る舞うことで、素人・玄人に関係なく、適切な利益を得ることができる仕組みになっています。通常のファーストプライス型のルールだと、相手の入札戦略や支払い意欲をうまく予想していないと、勝てるのに払いすぎてしまう、あるいは入札額が低くて全然勝てない、という状況が起こり得ますが、セカンドプライス型は、本人にとってベストな結果が保証されています。
ファーストプライスからセカンドプライスへと、大きなゲームチェンジが起きることによって、入札での最善な振る舞いが変わる。これは、ルールを変えると人々の行動を変えることができるゲーム理論のよい例ですね。
このように、駆け引きを数学的にきちんと分析するゲーム理論をうまく使えば、現存するシステムはそのままに、人々の行動を変化させることも可能かもしれません。
熊野:信用とマーケティングの関係は、非常に面白いですね。あえてちょっと意地悪な質問をすると、新商品といえども、それはあくまで顕在的な価値観の中で開発されていると思います。しかし、イノベーションを起こすなら、まだ世の中に顕在化してない潜在的なニーズからサービスを作る必要がありませんか?
例えば「孤独は嫌だ」という価値観は今の世の中に溢れていますが、孤独が何かという輪郭はなかなか見えない。そのような潜在的なニーズを正直に顕在化させる仕組みは、何かありますか?
安田氏:消費者自身も気づいていないニーズやペインを引き出すのは、非常に難しいですよね。スティーブ・ジョブズがiPhoneを発売したときのように、誰も想像できないところにガーンと新しいものを提示すると、これまで気づいていなかった欲求が生まれることがある。それは、消費者に寄り添っても出てこないんですよ。
そこを乗り越える新しい調査方法や、イノベーティブなアイデアの提案が求められるとき、匿名式でアイデアを募るのは、1つの手かもしれません。
参考になりそうな小ネタとして、2023年にノーベル経済学賞を受賞したクラウディア・ゴールディンさんの「ブラインド・オーディション」の研究をお話ししますね。
従来、オーケストラのオーディションは審査員が演奏者の姿を直接見て評価するのが一般的でしたが、演奏者が見えないようにスクリーンを置き、見た目がわからない環境で音だけで評価する「ブラインド・オーディション」を導入したところ、女性が選ばれる割合が大幅に増加し、審査員が無意識に男性を優先していたこと(アンコンシャスバイアス)が明らかになりました。ブラインド・オーディションは、現在では欧米の多くのオーケストラで標準的に行われています。
これをビジネスの現場に置き換えると、社内からアイデアを募るとき、多くの場合は記名式で、どの部署の誰から上がってきたアイデアかがわかりますよね。「若い人のアイデアは実現可能性が低いんじゃないか」とか「すでに実績を出している人のアイデアは優秀なはずだ」とか、色眼鏡で見ちゃっている可能性もある。また、パートタイム制の社員は通常フルタイム勤務の人に気を遣いがちですが、彼ら、彼女らはフルでビジネスに参加できない分、家族のケアや副業など外の世界を見ている人たちなので、フルタイムの社員より面白いアイデアが出てきてもおかしくない。ブラインド制だったら、性別や年齢、役職、フルタイム・パートタイム関係なく、よいアイデアが汲み取れますよね。
熊野:面白いですね。安田先生の話から、制度や仕組みのデザイン次第で、潜在的な力や多様な視点を引き出せることに大きな可能性を感じました。匿名性のアイデア募集は、ぜひ社内で取り入れてみたいです。
(後編へ続く)
対談者
安田洋祐(やすだ ようすけ)氏
政策研究大学院大学 教授
1980年東京生まれ。2002年東京大学卒業。最優秀卒業論文に与えられる大内兵衛賞を受賞し経済学部卒業生総代となる。米国プリンストン大学へ留学して07年Ph.D.(経済学)取得。政策研究大学院大学助教授、大阪大学准教授・教授を経て、25年10月より現職。専門はゲーム理論およびマーケットデザイン。American Economic Reviewをはじめ、国際的な経済学術誌に論文を多数発表。政府の委員やテレビのコメンテーターとしても活動。20年に「経済学のビジネス活用」を目指して株式会社エコノミクスデザインを共同創業。主な著書(共著)に『日本の未来、本当に大丈夫なんですか会議』(日本実業出版社, 2024年)、『そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。』(日経BP, 2022年)など。
アミタグループの関連書籍「AMITA Books」
【代表 熊野の「道心の中に衣食あり】連載一覧
【代表 熊野の「道心の中に衣食あり」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。
下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。
https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820