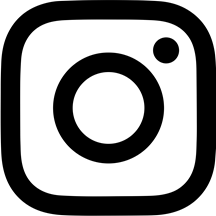延長戦かゲームチェンジか? 経済学者と語る、資本主義社会の未来予想図(後編)
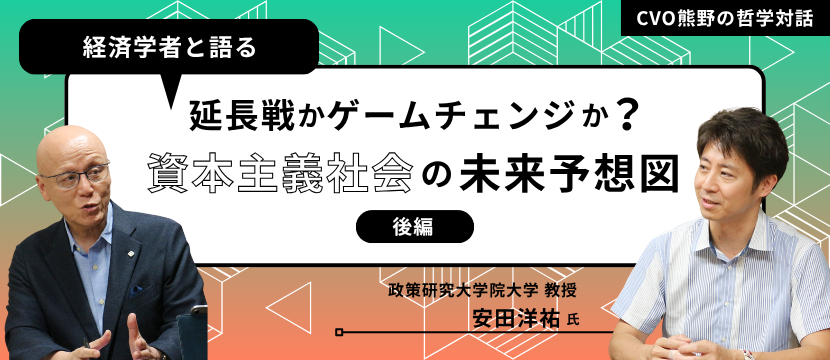
今回、当社代表取締役会長の熊野英介が対談したのは「ゲーム理論」や「マーケットデザイン」を専門とする、経済学者の安田洋祐氏。
資本主義や民主主義など、戦後日本を支えてきた社会システムのほころびが露わになる昨今。前代未聞のAI革命が起きるなか、日本はどう対応すべきなのか――?安田氏の経済学的知見と鋭い市場洞察に、熊野が持つ哲学的かつ事業家としての視点がクロスすることで、大局から時代の潮目を読む貴重な対談となりました。
(対談日:2025年7月7日)
<前編はこちら>
目次
社会課題の大局を見据え、人類がとるべき選択とは
熊野:資本主義が抱える課題に話を戻して、安田先生に質問です。
1990年代、特にリーマンショック以降、中国や東南アジア諸国で急速な工業化が進みましたよね。この動きは、生産資本の一部が先進国に集中する一方、その生産拠点が新興国に移転することで、先進国と新興国の経済格差が解消されるという見方を一部で生みました。
しかし、現実は異なり、教育機会の格差など新たな不平等が顕在化し、所得格差を示すジニ係数はむしろ上昇しています。
さらに、この格差の広がりと連動するように、インドやインドネシアといった国々で出生率が著しく低下している。これは、質の高い教育や医療にアクセスできる層ほど出生率が低下するという、新しいタイプの格差の現れではないかと指摘されています。この社会構造の変化について、安田先生の考えを教えてください。
安田氏:まず、格差をどう捉えるかですが、僕は人類の暮らしは単線的に改善していると感じています。一部、早くから経済的な繁栄を享受していた先進国では、確かに問題が発生していますが、飢饉が起きるたびに大勢亡くなっていた時代に比べて、平均寿命は延び、格差は大きく縮小しています。中国にしてもインドにしても平均的な暮らしぶりは上がっているなかでの格差だと思いますし、例えば「1人当たりの所得が10分の1だった20~30年前に戻りたいですか?」と聞かれたら、多くの人はノーと答えると思います。
格差を許容する資本主義こそが、経済発展のダイナミズムを生み出す側面があるのは事実です。ある程度、格差を許容しないと経済成長できないのであれば、おそらく大多数の人は、今の資本主義の仕組みを是とするんじゃないでしょうか。少なくともGAFAMやエヌビディア※は、貧富の差が大きなアメリカが生んだ大企業です。
※エヌビディア...1993年に設立されたアメリカの半導体企業。AI開発や自動運転技術など最先端分野で圧倒的な市場シェアを誇る。
これらを踏まえると、今後の理想は、暮らしも豊かになりつつ格差も抑えられる、いいとこ取りの仕組みを考えることですよね。
僕は、現状の資本主義の仕組みを維持したまま格差を解消するには、大きく2つの考え方があると思います。
1つは、お金の再分配を工夫する方法です。これは昔から多くの国で行われてきたことで、かつては日本でも所得税の最高税率が70%を超えていた時代がありますし、北欧では今も高い税率による再分配を続けています。ただ、本当にそれだけで十分なのかという疑問も残ります。最近よく話題になるのがベーシックインカムで、社会保障を最小限にして現金を定期的に一律支給する仕組みです。行政コストやインセンティブの歪みを抑えやすいため支持する学者も多い一方、同時に「市場中心の社会」を強めてしまい、自己責任の考え方が広がる懸念もあります。
もう1つは、そもそも市場でやり取りされるものを減らす「脱商品化」です。最近はGDPを見ても、教育や医療・介護など、市場で完全に価格が決まらないような、社会性の強いサービスが占める割合が高まっていて、ある意味でお金では買えないものが増えている時代です。ローカルで市場とは異なる制度が整ったとき、先ほど少し話題にしたような個人の貢献度が評価される仕組みができれば、脱商品化はより進むのではないでしょうか。
お金の物差しだけではないさまざまな価値基準のコミュニティや経済圏に属していれば、たとえ経済格差で不利になっても、お金とは異なる別の側面で支えられる可能性もあります。ただ、価値の計り方はまだ法定通貨と強く結びついていて、新しい価値の市場を作りにくいのが現状です。
熊野:なるほど。日本は今、資源枯渇と気候変動による《安定調達の限界》、格差拡大・高齢化・雇用不安による《社会的限界》、実体経済と金融経済の乖離による《市場拡大の限界》という3つの構造的な限界に直面していると思います。
これまでの経済成長を支えてきた社会システムの限界が露呈しつつあるいま、3つの限界を超える経済とは、どのようなものだと思いますか?
経済的な動機性だけでなく、前半でお話があった「信用革命」や、今おっしゃった、個人の社会的貢献度が評価されるような、社会的な信用が行動の動機となる、新しい運動法則を持った資本主義で、経済のダイナミズムを起こすことはできないでしょうか?
ミレニアル世代やZ世代と呼ばれるような今の若い世代では、どうせなら社会に貢献したいと思う人が増えているようにも感じます。限界効用逓減の法則※が働くように、年収がある程度あれば、物欲にも上限が生まれるはずです。そんな時代で「Aを買うよりBを買う方が社会が良くなるらしいよ」といった社会的な貢献欲求が生まれる市場を作り出して、買えば買うほど、作れば作るほど、社会がどんどん良くなっていく資本主義を実現するのは難しいですか?
※限界効用逓減の法則...消費する財やサービスの量が1単位増えるごとに、その追加分から得られる満足度(限界効用)が徐々に減少していくという経済学の概念。
安田氏:僕は、現時点ではまだ、そういった社会的な動機というのは、一部の富裕層に限られるんじゃないかと思います。ある程度ビジネスの世界で成功して、本人の暮らしぶりに関して不安がなくなってくると、社会的に意義のあるビジネスをスケールしたいとか、女性の社会活躍を推進するために雇用の仕方を変えたいとか、自分の暮らしを良くする以外のミッションを追求できるようになる。まずは自分が稼いで食べていくために勉強や就職活動を頑張る、という人が大半なのではないでしょうか。
ただ、日本の若者に限って言えば、就職に苦労しない点で他のアジアの国々とは状況がかなり違っています。日本ではまだ同じ会社で長く働くケースが多いので、社内で育成することを前提に、採用時点のスキルが低くても若い世代が採用されますよね。そうした背景もあって、日本の若い世代は社会的動機で仕事を選ぶ人も多いのではないでしょうか。
今、アメリカやヨーロッパなど多くの国では「ジョブ型雇用」が主流で、労働者は短期間で転職するのが一般的です。仮に5年間しか勤めてくれないとわかっていた場合、ハーバード大学出身だったとしても、経験や特別なスキルがない人を企業は雇わない。むしろ二流大学卒でも、すでに長年の実績があって即戦力になる人が重宝されるんです。そこで、学生たちは成績表をオールAにする、大学院に行って修士号や博士号を取る、あるいはNPOで経験を積むなど、たくさん努力をする。それでやっとよい仕事をゲットできるチャンスが出てくる。この厳しい就職市場が、欧米や中国、韓国では当たり前です。一握りのトップ大学に行かないと高い給与を稼げないとか、よい大学を卒業しても就職がうまくいかないとか、熾烈な競争社会の裏側には、労働市場や大学教育の在り方に問題があると思いますね。
熊野:なるほど。逆に言うと、そんな状況だから、アントレプレナーが生まれやすい側面もあるのでしょうね。私たちが生み出すべきは激しい競争社会ではなく、社会的動機性が発揮される市場でハングリー精神のある人財が切磋琢磨できる状況ですね。
デジタル後進国・日本が、AI革命でカエル飛びに組織変革?
安田氏:若者が就職に困らないことが関係するのかしないのか、日本の実質賃金はここ20~30年全く増えていません。
この背景には、生産性を思うように上げられていない面があります。いろいろな原因が考えられますが、ほぼ間違いなく原因の1つだと思われるのは、デジタル技術を全く活用できていないことです。スイスに拠点を置くビジネススクール「国際経営開発研究所(IMD)」が出している世界競争力ランキングやデジタル競争力ランキングを見ると、ビッグデータの利活用やデジタル技術という指標で、日本は毎年、ほぼ最下位なんですよ。
ただ不思議なのは、日本はブルーカラーの複雑な仕事を機械で代替して、工場を無人化・省人化していくのは得意だという点です。実際、トヨタ自動車の工場を見ても、極めて効率よく無人化・省人化できている。ではなぜ、日本企業がホワイトカラー業務では代替に失敗しているのか。これは真剣に考えるべき問題です。
1990年代のIT革命時に、アメリカはオフィスワークを定型化・デジタル化して、余った人員はどんどんリストラしていきました。もちろん失業者も増えますが、消費者の新しいニーズを掘り起こし、イノベーションを生み出す方向に人員を割けるようになれば、GAFAMに代表されるような生産性を高めた企業が登場して、また人を雇用する流れが生まれます。
日本では、余った人材を解雇する文化がないので、仮に労働者を代替できたとしても、やることがない窓際族みたいな人たちをたくさん生み出すことになる。だから、そもそも省人化しようとするインセンティブが働かなかった、という説はよく耳にしますよね。また「自分たちの業務には意味がなかったといわれたくない」という労働者からのプレッシャーもあったのかもしれません。その結果、今の日本で日々のオペレーションに忙殺されず、付加価値を生み出すためだけに時間をさける人員が、どれだけいるでしょうか。
熊野:今到来している生成AIのインパクトは、まさにホワイトカラーがどう働くか、という話につながりますよね。
生成AIの台頭によって、これまでの労働時間×資本による労働生産性から、価値×資本の価値生産性の時代への急速な移行が始まりました。今の企業経営において、人は資産ではなく人件費のカテゴリ、つまり経費として扱われていますが、本当にそれでよいのか?生成AIによるこのパラダイムシフトは、我々が「人はコストではなく資産であるということを証明できるのか?」という時代からの挑戦だと捉えています。
人間にしかできない領域、すなわち美意識や価値観といった企業文化性の醸成、信頼や共感などの関係性、信頼できるデータの収集と編集のメカニズムなどを、企業価値の源泉・コアに据えていかなければ、どのような大企業もこのAI化の波の中で淘汰されてしまうと思いますが、先生はどうお考えですか。
安田氏:おっしゃる通り、企業にかかる淘汰圧はますます強くなっていくかもしれません。1990年代のIT革命をうまく活用できなかった日本に、今度はさらに強力なAI革命の波が押し寄せてきてしまった。「IT革命すら実現できなかったんだから、AIも活用できずに終わる」というのが、標準的な見立てでしょうね。でも僕は、今回のAI革命でIT革命も含めた一足飛びの組織改革が可能になるチャンスもあるのでは、とも期待しているんです。個人的には、後者のリープフロッグ(カエル飛び)現象が起きるシナリオに賭けたいです。
例えば、どうやって省力化・無人化、あるいは複雑な業務を定型化していくのか。今までであれば、高いコンサルティング会社に相談をしないと出来なかった組織改革が、とりあえず月に20ドル払ってChatGPTに聞けばいろいろと建設的な提案を受けられるようになる。「こういう仕組みを作ればこれだけ時間を短縮できますよ」とか「割ける人員を減らせますよ」といった具体的な提案をAIがしてくれて、仕組み化のためのプログラミングコードも書いてくれたら、とりあえずやってみようとなりそうですよね。
日本の組織は面白くて、先行事例がないとなかなかゴーサインを出せない反面、同業他社が新たな取り組みを成功させると、それを真似しないのはものすごくネガティブに感じる風潮があるんです。試行錯誤する組織の中から、ひとたびブレイクスルーが起きれば、右にならえで日本の組織全体が一気に変わっていくかもしれません。
熊野:日本の伝統的な意思決定の仕組みでは、上から下へ伝わる途中で情報が何度も中間管理職で整理され、事業部でまとめられた後に投資家に説明され、投資家の承認を得て......という間のびしたプロセスが必要でした。これに対して今は、生成AIを用いて可能かどうかの判断を即座にしながら、上からの指示をすぐに試すことができる。この意思決定の短縮化が、日本の将来に可能性を与えるということもありますか?
安田氏:はい、あると思います。あといくつか、日本にとって明るい指標もありますよ。まずは、ハードインフラの充実です。日本のモバイルブロードバンドの普及率や、人口あたりのロボットの数は、IMDの調査でどちらも世界トップクラスなので、ソフトウェア部門での進化を実現する際に、ハード面のインフラがボトルネックになることはほぼありません。
そしてもう一つ、失われた30年※と呼ばれる時代でも、日本が世界で優位性を示してきたのが「ビジネスの複雑性」です。ハーバード大学が公表している経済複雑性のランキングにおいて、1995年以降、日本はほぼ一貫して世界1位を維持しています。
※失われた30年...1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、日本経済が長期にわたる停滞に苦しんだ約30年間を指すことば。
これは日本における、ボトムアップ型やすり合わせ型の組織構造がプラスに働いた結果でしょう。先ほどの話とつなげると、複雑な意思決定を複雑なままこなすことに日本の組織は長けている。ただ、それも人員に余裕があるからこそできる話で、これから先、より複雑なものを生み出していくために、機械やAIでできることは、極力人間以外に任せて、空いている人員をより一層複雑な仕事に振り分ける必要がある。その複雑さは、単に企業の時価総額に直結するものでなくても、まさに御社のテーマでもある社会との共生であるとか、どうやって金銭価値とは違うものを訴求していくかとか、そういったアイデアの創出にも必要ですよね。
最後にもう1点。失業率が低いからこそ、AIなどの新技術に抵抗するラダイト運動※のような動きが起きにくいと思うんですよね。90年代のIT革命時はバブルがはじけた直後で人が余っていたので、ExcelやWordで仕事を効率化して人員を削減するという方針を取りにくかったけれど、今は逆に人が足りていない。労働市場において需要の創出ではなく効率化が求められる現状は、日本経済の強みになり得ます。
※ラダイト運動...19世紀初頭のイギリスで、産業革命によって職が奪われることを恐れた労働者たちが起こした、機械の打ち壊しを伴う運動。
いろいろな方面で期が熟した今、企業はAI活用などによって生み出したリソースを、暮らしを豊かにするビジネスアイデアの醸成に投入してほしいですね。
熊野:アミタでは社員に「会社は仕事を覚える場所ではなく、生きていくために大切なことを学ぶ場所」だと伝えています。
例えば新入社員は、最初の9か月間、寮で共同生活しながら、様々な独自の研修を受けるんです。一例として、「レゾンデートル研修」というプログラムでは、「平等」「公平」「個人」「個性」「権利」「義務」「自由」「自立」という8つの言葉の定義や相関関係を紐解き、世界の本質や人間の存在意義について深く考える機会としています。これ、実際にやってみるととても難しいお題でしてね、毎年、脳みそに汗をかくくらいウンウン唸りながら取り組んでいますよ。
また、20~30代を中心に、新たな価値創出人財を育成する「桃栗研修」を2024年から実施しています。社員は合流後3年間、企業哲学や礼儀礼節、会計やマーケティングの基本、営業心得といった基礎研修を受けた後、「未来デザイナー」「Do タンカー」「タウンマネージャー」「ミッションエンジニア」という4つの職種から1つを選択し、専門的かつ実践的なプログラムを経て、8年後には自ら新たな事業を生み出すことを目指します。

熊野:こうした研修を受けた社員が増えることの効果は、企業文化の醸成や事業創出のほかにもう一つ、社内外の取引コストの削減があります。取引コストとは、前半でも少し触れましたが、経済取引にかかる調査や探索費・交渉費・監視費などを指し、広義には広告宣伝費や採用コスト、社内合意に必要な調整コストなども含まれます。企業哲学を理解した本質主義の社員が、生成AIを有効活用し、体系的な事業の構想構築を実践すれば、社内外の意思疎通や合意形成、共感獲得が容易になり、その結果、取引コストの大幅削減につながると思うんですね。
AIが単なる効率化だけでなく、仮説検証や類推といった高度な分野を補完する時代だからこそ、人間がどのような視座で何を学び、何を経験していくのか、ということが重要になってくると考えています。
安田氏:レゾンデートル研修、とても面白いですね。僕も興味があります(笑)
複雑で多面的な日本の編集力が、工業をサービス化する時代
熊野:世界がますます複雑化する時代で、これからの経済には「シンプルなものをよりシンプルに」とか「確実なものをより確実に」ではなく「複雑なものを複雑なまま扱うために、人間がAIをどう使うか」という点が重要だと改めて感じました。
日本は天変地異が多い国です。全く思い通りにならない状況下で社会を築いてきた日本人には、歴史的に培ってきた「編集力」があると思います。例えば神仏を習合させる、漢字とひらがなを組み合わせるなど、複雑で多面的な編集を平気でやってきた日本人のDNAは、これからの工業を無形性と有形性を合体した領域に昇華させるのではないでしょうか。家電の領域をすべてモバイル化することで外出中も自宅の状況がわかるとか、車に乗れば血圧が測れるとか、個人の趣味に合わせて家電をカスタマイズできるとか......。こうした、工業がサービス化する時代が来ると思うんです。
安田氏:それは間違いないですね。本来、暮らしを豊かにする消費活動にうまくつながるのなら、物自体は購入しなくてもいいわけですから。モノからコト(サービス)への変化はごく自然な現象だと思います。
例えばテレビを買う人の多くは、居間にテレビというモノを置きたいわけじゃなくて、番組視聴というサービスを享受したいわけです。そこで消費者としての体験価値を向上するために重要なのは、よいテレビを買うことではなく、テレビのパフォーマンスを引き出すことですよね。消費者はモノを買っているつもりでも、突き詰めると、モノから享受できるサービスを購入している。
とくに近年はモノがインターネットとつながるという、市場にとって大きなゲームチェンジが起きました。ユーザーごとに適切なサービスを提供できるようになったので、今後はますます工業がサービス化していくと思います。
熊野:日本の工業は今後「編集力」で世界と戦える気がするのですが、いかがでしょうか?
安田氏:それについて僕はやや悲観的です。残念ながら現時点において、日本の企業はカスタマイゼーションの視点でうまくパフォーマンスを出せていません。
インターネットを通じたカスタマイズサービスの多くは言語に依存しています。例えば、検索サービスや音声アシスタントは、英語や中国語、スペイン語など話者の多い言語が有利で、日本語は話者が少ないためそもそも不利なんです。
一方で、言語にあまり依存しない分野、例えば車の自動運転や介護ロボット、トイレやお風呂の自動化技術などには活路がありそうですね。ただ、これらの分野は法的規制の影響も大きいので、産官がうまく連携しないと、技術的には勝てるはずの競争も勝てなくなってしまうのでは、と懸念しています。
熊野:なるほど。その視点は重要ですね。AI革命で社会が大きく揺らぐ今、私たちは技術を使うのか、それとも使われるのか。その瀬戸際で、安田先生の指針を知ることができてよかったです。今日は本当にありがとうございました。
安田氏:こちらこそ、どうもありがとうございました。
対談者
安田洋祐(やすだ ようすけ)氏
政策研究大学院大学 教授
1980年東京生まれ。2002年東京大学卒業。最優秀卒業論文に与えられる大内兵衛賞を受賞し経済学部卒業生総代となる。米国プリンストン大学へ留学して07年Ph.D.(経済学)取得。政策研究大学院大学助教授、大阪大学准教授・教授を経て、25年10月より現職。専門はゲーム理論およびマーケットデザイン。American Economic Reviewをはじめ、国際的な経済学術誌に論文を多数発表。政府の委員やテレビのコメンテーターとしても活動。20年に「経済学のビジネス活用」を目指して株式会社エコノミクスデザインを共同創業。主な著書(共著)に『日本の未来、本当に大丈夫なんですか会議』(日本実業出版社, 2024年)、『そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。』(日経BP, 2022年)など。
アミタグループの関連書籍「AMITA Books」
【代表 熊野の「道心の中に衣食あり】連載一覧
【代表 熊野の「道心の中に衣食あり」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。
下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。
https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820