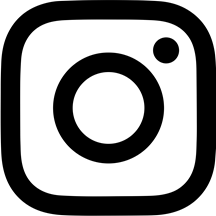Human Co-becoming─人間は他者との関係性の中でこそ存在できる─(前編)

産業革命以降、世界は西洋由来の哲学を軸に発展してきました。自然を道具とみなす人間中心主義、個人の自律、経済的発展がもたらす豊かさ──。私たちが日ごろ、当然の前提として受け入れている社会の価値観は、果たしてどこまでゆるぎないものなのか。当社代表取締役会長・熊野英介が、哲学の歴史を振り返り、その在り方を根底から研究する哲学者・中島隆博氏と対談。人間社会の在り様を、根本から問い直しました。
(対談日:2025年10月9日)
目次
- ぶつかりあい変容する、多層的な中国哲学の世界
- 中国に儒教ブーム到来、日本の経営哲学にも通じる「徳治主義」
- 現代は帝国・王権時代への揺り戻し?
- 「国の株式会社化」は、民主主義を劣化させるか
- 他者とともに変容していく人間観「Human Co-becoming」
- 自分を超えた存在を感じる「宗教なき宗教性」
ぶつかりあい変容する、多層的な中国哲学の世界
熊野:今日は尊敬する中島先生との対談が叶い光栄です。私は今、世界が大きな文明の転換期にあると感じています。正解が存在しない混沌の時代においては、自ら正解をつくり出していかなければならない。では、どこに「価値」の指針を置けばよいのか。これまでは産業革命以降に発展した西洋由来の哲学が中心にありましたが、今はもっと多くの視座で物事を見る必要があると思うのです。東アジア哲学を中心に、幅広い哲学を研究されている中島先生のお話をぜひお聞きしたいです。
中島氏:こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。
熊野:司馬遼太郎が「中国の古代、とくに漢代までに、人間が考えうる政治や制度のほとんどが一度は試されてしまった」という趣旨の発言をするほど、中国の漢の時代には、多様な文明がぶつかり合い、人間模様が複雑に交差する中で、多層的な哲学が生まれましたよね。
老子の道家、孔子の儒家、前漢時代に伝来した仏教など、中国哲学にはさまざまな思想が存在しています。さらには、元や清など異民族の支配を受けたこともある。先生はこの複雑な状況をどのように読み解き、編集してこられたのでしょうか。まず、その面白さについて伺いたいです。
中島氏:ありがとうございます。儒家・道家といった思想の分類は、前漢に、司馬遷の父である司馬談が「六家の要旨」としてまとめています。中国という国家の形は、漢代においてある程度定まったといってよいでしょう。
しかし、ご指摘の通り、中国ではさまざまな思想が入り混じり、たびたび思想の衝突も起きています。例えば、儒家と道家の間の争い、あるいは儒家と墨家の争い、そして仏教やキリスト教が入ってきたときの争い。私は、このような思想間の「論争」を主な研究テーマとして扱ってきました。
どの思想も前提にしている世界観が違うので、やはりどこか相容れません。しかし、論争するということは、お互い食い違いながらも「対話」をしているわけですね。私は、その食い違いをクリアにしていくことで、各思想の特徴的な姿が見えてくると思ったのです。
そこで、その論争の過程を現代まで追いかけ、『中国哲学史』(中公新書、2022年)としてまとめてみました。1人の著者が中国哲学史を古代から現代まで扱うことは最近めったにないのですが、まあやってみようと思った次第です。
武田泰淳という作家は、1943年に出版した『司馬遷 史記の世界』の中で、「司馬遷が『史記』で描いたのは"人間天文学"である」と述べています。つまり『史記』は、人間が入り乱れる姿を、まるで宇宙を観測するように描いたものだ、ということです。私はその指摘に、非常に強いインスピレーションを受けましたね。
熊野:共産主義が登場したときも、世界では激しい大論争が起きましたよね。AかBかという強い対立がありながらも、いわばブラウン運動のように、さまざまな意見や力がぶつかり合って揺れ動くなかで、最終的にはその時代の均衡点へと収まっていく。そうして、各時代の空気が形づくられていくのだと思います。
しかし、中国らしさというものは、こうした衝突をいくつ経ても、決して失われません。その根底で共有されてきたフレームとは、いったい何なのでしょうか。
中島氏:どちらかが一方的に変化させるのではなく、お互いがお互いを変形し合うのだと思います。例えば仏教もキリスト教も、中国に入ると「中国化」しています。また、マルクス主義さえも中国的に変容しました。
その核心にあるものは何か、という問いに対して、私はやっぱり中国独自の「人間観」だと思います。
熊野:中国独自の人間観。それはどういうものですか?
中島氏:この人間観を表すために、最近私は「Human Co-becoming(ヒューマン・コ・ビカミング)」という言葉を用いています。人間とは根源的に社会性を有するものであり、他者との関係性の中でこそ存在できる、という考え方です。これは、近代の西洋哲学が前提とする「自律した個人」とは真逆の人間観です。
中国に儒教ブーム到来、日本の経営哲学にも通じる「徳治主義」
熊野:なるほど。中国独自の人間観を深める前に、1つ質問してもよいですか。
いまの中国を見ていると、家族や一族を最優先に考える価値観が強いように感じます。まず家族があって、その次に社会があるという......。そのあたりは、どう捉えればよいのでしょうか。
中島氏:確かに中国では「宗(そう)」という概念、つまり一族を中心とした共同体の考え方が非常に大きな意味を持っていますね。これは儒教的な価値観に由来していると思います。
例えば毛沢東は「儒法闘争」という言葉を使って、儒家と法家の闘争を説き、自分は法家の側に立つと宣言しました。法家とは、厳格な法律によって統治する思想で、強い権威主義ではありますが、ある意味で平等な法による支配を目指しています。封建的な身分制度や秩序は終わらせる、と主張したわけです。
しかし、多くの研究者は、毛沢東自身が理想としていたのは結局「儒家の聖人像」なのではないか、とも指摘しています。つまり、儒家的な思想を完全に排除しきれなかったという見方が主流なんですね。
熊野:中国では、秦の始皇帝以来、厳格な法治主義で政治が行われてきましたが、それに皆が疲弊した結果、次の段階として儒教の「徳治主義」──人の徳によって社会を治めるという考えに移っていったのですね。
中島氏:はい。毛沢東が率いる中国共産党も、表面上は法家的な統治を強調していましたが、文化大革命で大きな失敗を経験します。その後、鄧小平が立て直していく過程で、儒教が再評価され、復活していきました。いま中国は"儒教ブーム"と言ってもよい状況で、習近平政権も"新しい二十四孝"といった儒教的な方向性を掲げています。スコアリング制度(社会信用スコア)が中国では登場していて、親孝行など儒教的な徳目を高く評価する仕組みが、社会にシステムとして組み込まれているのです。
熊野:日本が近代化を進めた時代でも、合理主義こそ導入されたものの、経営の現場では結局「人徳」でまとめようとする傾向がありますよね。工業社会的な合理性や実力主義だけでは人を動かせない。そこに情理や徳を重視する経営思想が出てくる。松下幸之助や稲盛和夫も、まさにその流れの上にいる気がするんです。
中島氏:私も、日本は近代化のプロセスで同時に儒教化が進んだと考えています。これは18世紀末、寛政の改革あたりから始まった流れで、明治維新でも政府は儒教を国家理念として強化しようとしました。教育勅語がその典型ですね。ただし、あれは国家主義的な儒教で、孟子のような民衆からの変革を重視する儒教とは少し異なりますが。
そして、おっしゃるようにビジネスの世界でも儒教は重視されています。渋沢栄一が唱えた「論語と算盤(そろばん)」、つまり徳と経済は切り離せないという思想はその象徴です。それが松下幸之助、稲盛和夫へと受け継がれていったのだと思います。
現代は帝国・王権時代への揺り戻し?
熊野:いま世界は、中国的な国家資本主義、つまり国家が計画的に資本を集中させ、経済力を高めていくモデルが力を持っていますよね。その勢いで中国は日本を抜き、アメリカの足元まで迫った。そのタイミングでトランプ氏が登場し、アメリカ自身も新しいあり方を模索し始めた。プーチン氏もまた、中世のような国家運営のスタイルへ戻っている気がします。
政治面では、選挙で選ばれた政治家ではなく、血縁の人物を側近に置くなど、影響力のある国々がそれぞれ帝国や王政時代に回帰しているようにも見える。今のこの時代の動きを、歴史の視点からどう読み解けばよいのでしょうか。
中島氏:トランプ氏は就任して間もない頃、自身のSNSで「国王万歳!」と書き込んだでしょう。21世紀に入って、自らを「王」と名乗る政治家が登場するとは想像していませんでしたから驚きました。時代錯誤も甚だしいわけですが、しかし現実として、アメリカ社会がトランプ氏を必要としている。プーチン氏も習近平氏も同じで、皆「王」のような存在として振る舞っていますよね。
それは、社会全体が近代から離れ、もう一度前の時代へ戻ろうとしているのではないでしょうか。どれも近代国家の体裁をしていますが、実態は違う。
熊野:それは、アンシャン・レジーム(フランス語で「旧体制」意味し、フランス史においてフランス革命以前を指す)のような、旧体制への揺り戻しなのでしょうか。
中島氏:揺り戻しだと思います。本当に驚くべきことが目の前で起こり、非常に戸惑います。
熊野:中島先生ですら戸惑う世の中ですが、このまま進んでいくのでしょうか。
中島氏:いや、揺り戻しのままで終わるとは到底思えません。例えば「トランプ関税」の違法性について、アメリカでは裁判になっていますよね。関税で経済を調整する発想自体が、もはや時代遅れでもあります。
1829~37年にアメリカの大統領を務めたアンドリュー・ジャクソンも、まさにトランプ氏のようなポピュリストでしたが、当時の思想家、アレクシ・ド・トクヴィルは『アメリカの民主主義』で「アメリカは草の根の民主主義が強い国で、それを支える制度もしっかりしている」と評価していました。私もそこに期待していて、どこかのタイミングで今の体制は反転する気がしていますね。
「国の株式会社化」は、民主主義を劣化させるか
熊野:いまトランプ氏を支持している層は、国への不満を多く抱えているとも言われています。風説の域かもしれませんが、国民を満足させることが国家の仕事だとするなら、もっと「顧客志向」になって、株式会社のように国を運営すればいいのではないか?そんな議論がアメリカの一部で出ていて、一定の賛同もあると聞きます。
確かに国民の満足度は上がるかもしれませんが、顧客は社長にはなれませんよね。つまり民主主義が劣化してしまう。国民の満足さえ得られればいいという、ある種の依存的な社会は、まるで新しい王権社会のようにも感じます。資本主義とそれを基盤に成立した民主主義が、250年ほど経った今、一部で「国家運営=企業運営」という発想が生まれている現状をどう考えますか。
中島氏:まずは、資本主義と民主主義の相性を考えなければなりません。1970年代のアメリカや、その後の日本を見ていると、多くの人は「民主主義と資本主義はウィンウィンの関係だ」と考えていたと思います。しかし原理的に見れば、民主主義は平等を絶対的な価値としている一方、資本主義は利益をより多く得た者が勝つという仕組みです。
そうすると本来は相容れないものかもしれません。経済が成長を続けていた時期に、偶然ウィンウィンの状況が成立していただけだという理解もあります。
資本主義を突き詰めれば「権威主義で一気に決めた方が効率がいい」という議論になります。それは中国やロシアのやり方と近いものです。しかし、それは民主主義の真逆です。
資本主義は社会システムの中の一つにすぎません。ですから、他の多様なシステムと調和して機能しなければ、社会は急速に劣化していくでしょう。もし私たちが「民主主義的な社会の方が多くの人に平等に開かれていて、人々の幸福に寄与する余地がある」と信じるなら、社会を丸ごと資本主義化してはならないと思います。
他者とともに変容していく人間観「Human Co-becoming」
熊野:経済学者のヨーゼフ・アロイス・シュンペーターは「資本主義は成功すればするほど失敗する。なぜなら、やがて社会主義化するからだ」と言いました。勝者は自らの既得権益を守るためにイノベーションを望まず、自分たちに都合の良いルールを作り始めるため、社会主義化していく、という指摘です。いままさに、社会はそういう方向に進んでいると思うんですよ。
しかしそれは、カルヴァン主義(神の絶対主権を重視し、神によって救われる"選ばれし者"と地獄に落ちる"見捨てられた者"があらかじめ決まっているという"予定説"を提唱)のような、西洋的な思想の延長線上にある価値観のように思えます。今の時代には、先ほど先生が話された Human Co-becomingのような価値観、つまり人間観そのものの転換が必要なのではないでしょうか。物事の捉え方、認知が大きく変わらない限り、この問題は解けない気がするのですが、いかがですか。
中島氏:そうですね。資本主義は、しばしば「ホモ・エコノミクス(合理的な経済人)」という架空の人間像を前提にします。でもそれは、人間を極端に単純化したフィクションであり、そんな存在はどこにもいません。だから、ホモ・エコノミクス的な人間観から離れて、人間観そのものを作り直さないといけないと思います。
私が Human Co-becoming を提唱しているのは、人間の価値がそこで開かれ、幸福へとつながっていくと信じているからです。それは、一人ひとりが所有を積み上げて豊かになる考え方とはまったく逆です。所有は人を幸せにしない。物や情報をたくさん持てばよいという話ではなく、むしろ所有から離れて、人と共有することや、人と共にいることの意味を深めていく。その方向に進まないと、社会は持続できないと思います。
熊野:Human Co-becoming とは、他者がいてはじめて自分が成立する。つまり、自分が自分であろうとすればするほど、他者の存在が必要になる、ということですか。
中島氏:そうです。他者と共に自己変容していくことで、より良い方向に成長していく。
熊野:その「関係性」こそが重要だということですね。
中島氏:その通りです。
自分を超えた存在を感じる「宗教なき宗教性」
熊野:現代は、人々の気持ちが不安によってコントロールされていると思うんですよ。政治も経済も、不安をあおることで「そっちよりこっちだ」と誘導する。
今の社会は、人との「関係性」よりも、「お金」や「権威」などで自分のシェルターをつくってしまった方が楽だという考えのもと、分断と対立が生まれていますよね。でも、本当はそうじゃない。やっぱり他者との関係があってこその自己変容だ、と。
中島氏:不安を抱えていると、人は確実なものや手触り感のあるものに飛びつき、それを持つことで安心を得ようとします。
最初に「孤独担当大臣」が登場したのはイギリスで、その次が日本だったと思います。それだけ、人々が孤立し分断されているということです。日本は思った以上に孤独な社会になってしまった。だからこそ変えなければいけないのが「ソーシャルイマジナリー(社会的想像)」、つまり私たちの社会を見る認知のあり方です。
熊野:そこですね......!人が人として存在する意味に気づき、不安の流れを押しとどめ、安心を自分たちでつくり出していくためのヒントはありますか?社会の見方は、どのように変わっていくのでしょうか。
中島氏:気づきの芽はいろいろな場所にありますが、私はある種の「宗教性」のようなものが重要だと思っています。
つまり、私たちは自分だけで完結しているのではなく、自分を超えたものの存在を感じるということ。神かどうかはわかりませんが、確かに存在している「何か」。私はそれを「宗教なき宗教性」と呼んでいるのですが、それがとても大切だと思います。
他者というのは、お互いに関与する関係性の人を指します。エンゲージメント(他者や世界に関与すること)の感覚を取り戻すことが大切です。
熊野:工業社会がつくり出したリアリズムは、触れられるもの・見えるものに重きを置き、「縁起」のような目に見えないものは切り捨ててきましたよね。
中島氏:大事なのは、人間の根源的な社会性をもう一度思い起こすことです。例えば、今、私たちは日本語で話していますが、これは私が発明した言語ではない。赤ちゃんのときに他者に教わり、共有させてもらっている。もし私が私的言語を発明しても、誰も理解できない。言語を使っていること自体が、実は人間の根源的な社会性をよく示していると思います。
心だって同じです。私は自分の心を所有しているわけではない。私たちは「共にある心」を生きているわけですよ。共有しているのです。
身体も同じです。「私の身体」なんて軽々しく言いますけどね、私たちは毎日他者を食べ、常に入れ替わりながら存在しています。大きなエコシステムの中の1つであって、目に見える形で飛び出したものが身体にすぎないと思うんですね。
中島氏:人間を観察すれば、根源的な社会性が見えてくる。そこを出発点にするべきです。
中国哲学が面白いのは、「感情が豊かでなければならないこと」を徹底して追究するところです。泣くべきときに泣き、喜ぶべきときに喜ぶ。情を厚くするにはどうしたらいいか、これが究極のテーマなんです。
熊野:やっぱり「人間観」が非常に重要なんですね。
中島氏:徳が求められる場面でも、情がなければ機能しない。共感し、感情を共にすること。それが人間にとって決定的に大切だと思います。
アダム・スミスは『国富論』で「見えざる手」という表現をしましたよね。あれはしばしば「神の見えざる手」と言い直されますが、「神」とはどこにも書かれていません。最近の解釈では、それは「共感」のことではないかと指摘されています。言われてみたらそれも当然のことで、スミスは『道徳感情論』の著者でもあるんです。資本主義は共感や感情、人と共有する何かにつながっていなければうまくいかない──。スミスはそのことを見抜いていたわけですね。
(後編へ続く)
対談者
中島隆博(なかじま たかひろ)氏
東京大学東洋文化研究所 教授
哲学者。1964年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中途退学後、東京大学文学部助手等を経て、2014年から現職。専門は中国哲学、日本哲学、世界哲学。経団連総合政策研究所研究主幹として資本主義・民主主義に関しても研究を行う。主な著書に『中国哲学史』(中公新書、2022年)、『日本の近代思想を読みなおす1 哲学』(東京大学出版会、2023年)など。
2026年7月28日(火)中島氏が登壇
経営者のための哲学&価値創出フォーラム「羅針盤フォーラム」
第1回「知性の羅針盤」 ~マルチエージェントAIがもたらす人間拡張とは~
アミタグループの関連書籍「AMITA Books」
【代表 熊野の「凌雲之志」】連載一覧
【代表 熊野の「凌雲之志」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。
下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。
https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820